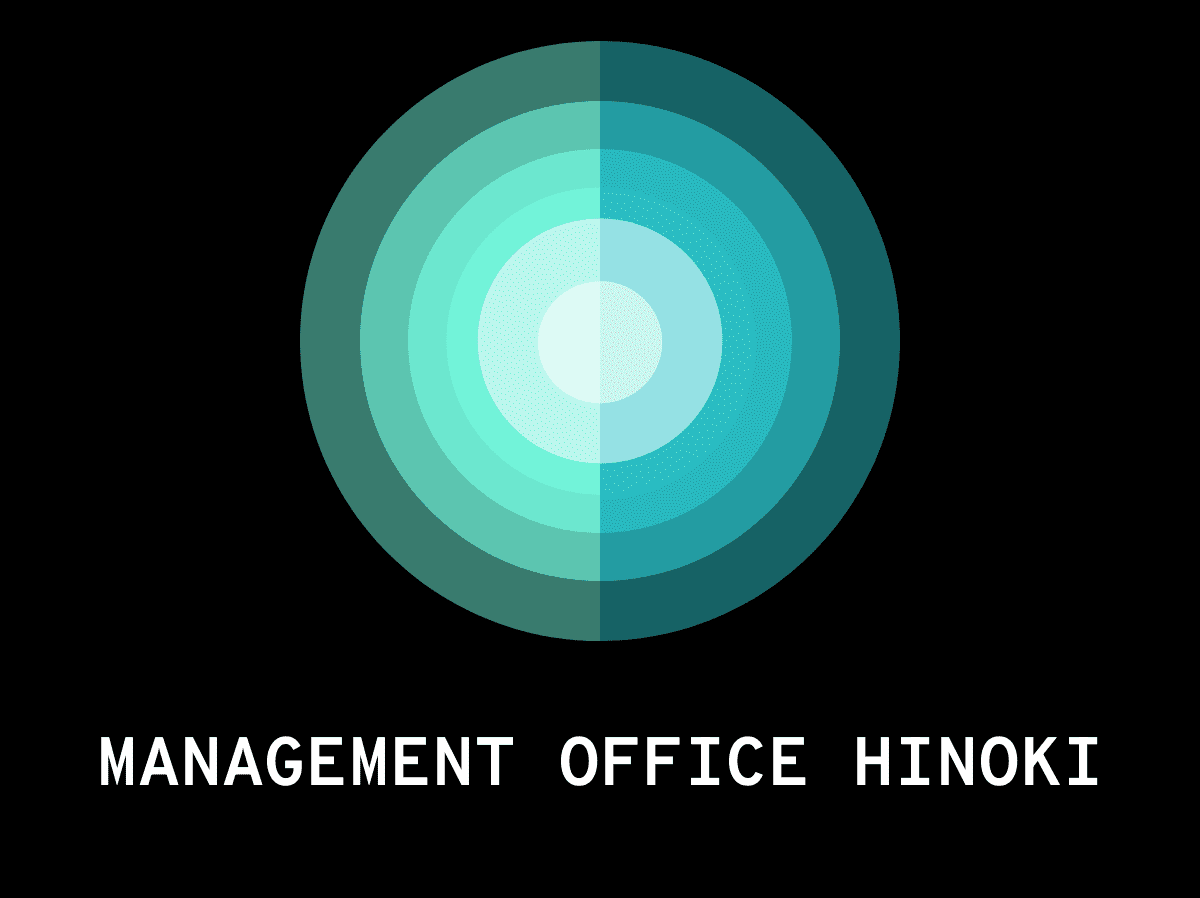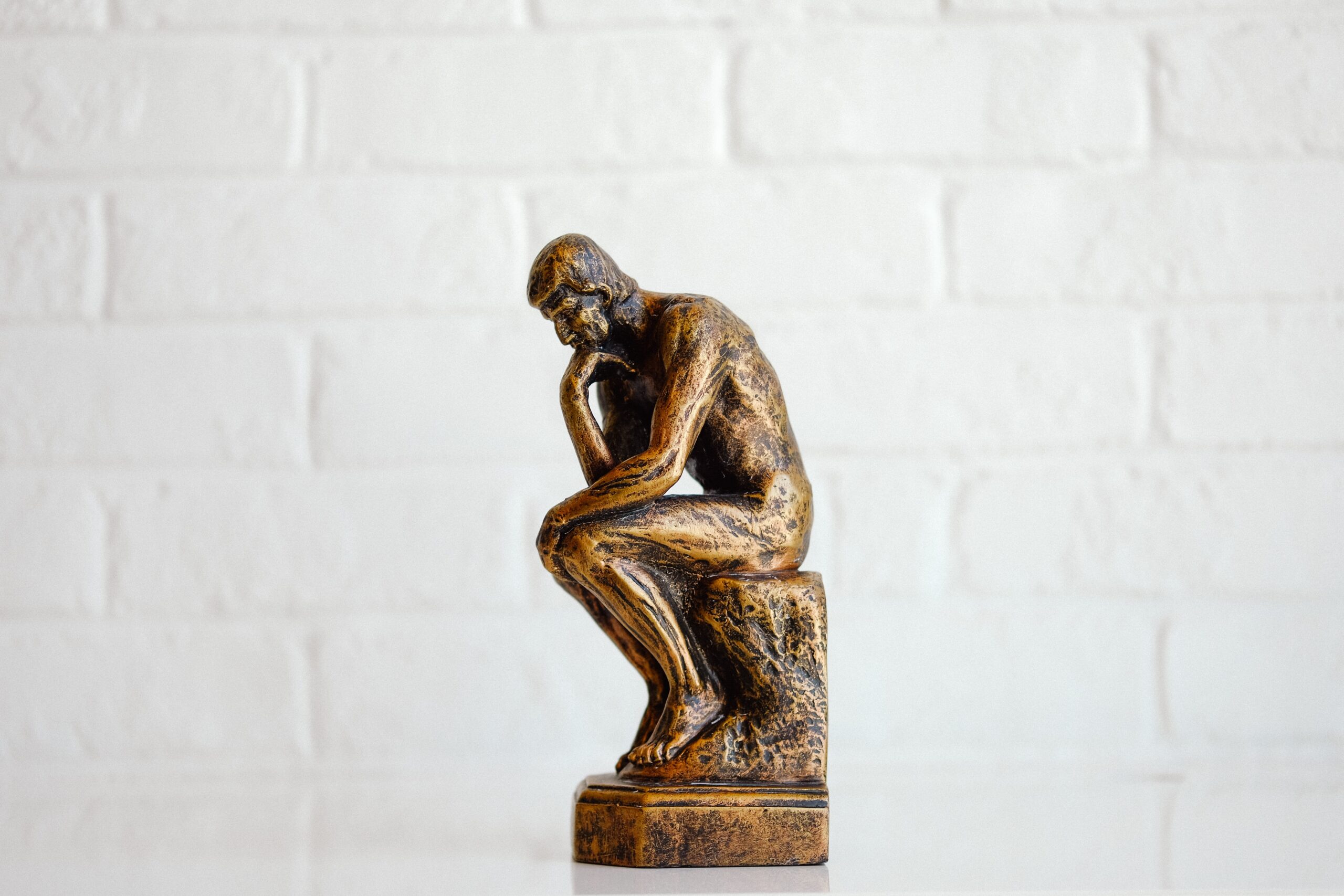こんばんは。10月も残りわずかとなりました。秋田はだいぶ気温が下がってきた。冬の足音が徐々に近づいてきている。秋田に限らずですが、東北の冬は本当にきびしい。寒いし吹雪の時はなかなか出かける気にならない。だが、私は冬生まれということがこともあるかもしれないが、冬が好きだ。あったかい部屋にいて飲む、おいしいお酒とあったかい鍋、それだけで幸せな気分になる。それだけでね。
あとは冬の静けさも好きだ。家にいるととても静かな時間を過ごせる。四季の中でもっとも勉強に向いている季節だと勝手に思っているわけであります。今年の冬はおそらくですが、とてもきびしい冬になるでしょう。世相は暗く、出口が一見見えないほど暗いはず。でもね、イギリスの宰相チャーチルはかく語りき。
現在我々は悪い時期を通過している。事態は良くなるまでに、おそらく現在より悪くなるだろう。しかし我々が忍耐し、我慢しさえすれば、やがて良くなることを私は全く疑わない。
ウィンストン・チャーチル
秋も冬も激動の展開が予想される世相ですが、元気にがんばりましょう。
さて、今日は一冊の本をご紹介。未来予測・国際情勢・マーケット分析などを中心に事業を展開しており、いつもお世話になっている国際派シンクタンク、株式会社原田武夫国際戦略情報研究所・原田武夫さんのご紹介で知りました。その名も「感動CX」。分厚い本でしたが、読んでよかった。今、現在事業を展開されている事業者さん、経営者層は必見かと。
なぜこの本を読んだ方がいいか?それは「CX(カスタマーエクスペリエンス)」の向上こそ、これからの時代を企業(個人事業主含)生き抜くために必須となりつつあるからだと。以下、本著のあらすじを公式サイトから引用。
感動CX | 東洋経済STORE (toyokeizai.net)
顧客を驚かせ、感動を与え続けるための“徹底攻略本”「顧客目線」という合言葉とともに、CX向上をテーマに掲げる企業が増えている。「CX向上に本腰を入れない企業は、淘汰される」という声は、日に日に増しているが、CXと切っても切り離せないDXに向けた活動で、成果をあげられていない日本企業も多いのが現状である。DXに向けた変革活動を前進させるためにも、本書では「CX思考」について深掘りしていく。本書内では、ベイカレント・コンサルティングが蓄積してきたデータや知見から、顧客の消費行動を分析し、企業戦略・事業戦略の根幹となるCXの組み立て方について解説。先進的な企業事例を多く取り上げ、その成功の秘訣にも迫る。事例・アカデミックの両面から「CX思考」について切り込んだ1冊だ。
今は本当にどの事業者にとっても大変な時代です。しかしながら、それを嘆いてても何も解決につながらない。ではどうするか?この本にある通り、1つの打ち手としてCX向上はテーマになっていくのではないか?部分的にやり方を改善するだけでは一時しのぎに過ぎない。
例えば、多くの飲食店がコロナ禍をきっかけにテイクアウトサービスをはじめました。私が暮らす秋田でもそうです。だがしかし、それは「CX」の視点が入っているだろうか?調査はしていないので分かりませんが、ほとんどの飲食店はコロナ序盤に比べて、テイクアウトサービスの勢いは最近なくなってきているのではないかな?なぜ、そうなるかというと理由はシンプル。顧客の期待を超え続けるサービスを提供することができなかったからと推測できる。
消費者がコロナ禍のテイクアウトサービスに飽きたわけではない、時間が経つにつれてベネフィット(顧客にとってのうれしさ)よりもコストが上回ってしまったので利用する人が徐々に減っていったのではないだろうか?こうした状況に対して本著は明快な方針を示してくれる。
つまり、サービス提供企業としては、移ろいゆく顧客が感じるベネフィットに適う要素を提供し続け、CXの価値が低下しないように取り組んでいく必要がある。モノを売ることが一旦のゴールであった既存ビジネスとは違い、現在のビジネスは購買やサービスの利用開始が顧客との長い関係のスタートにすぎないと心得る必要がある。
感動CX 21Pから引用
モノが売れない時代と言われて久しいが、それでも売れている企業はある。規模は関係なく、ビジネスの場所も関係ない。共通点は「CX」だ。その他にもこの時代を生き残るために必要な様々な考え方が本著では紹介されています。厳しい「冬」を乗り越えて、それでも顧客に価値を届けたいと強く願うあなたは必読。一緒に乗り越えましょう。この本は本当に有益な情報が盛りだくさんでしたのでまた紹介いたします。お読みいただきありがとうございました(^^)