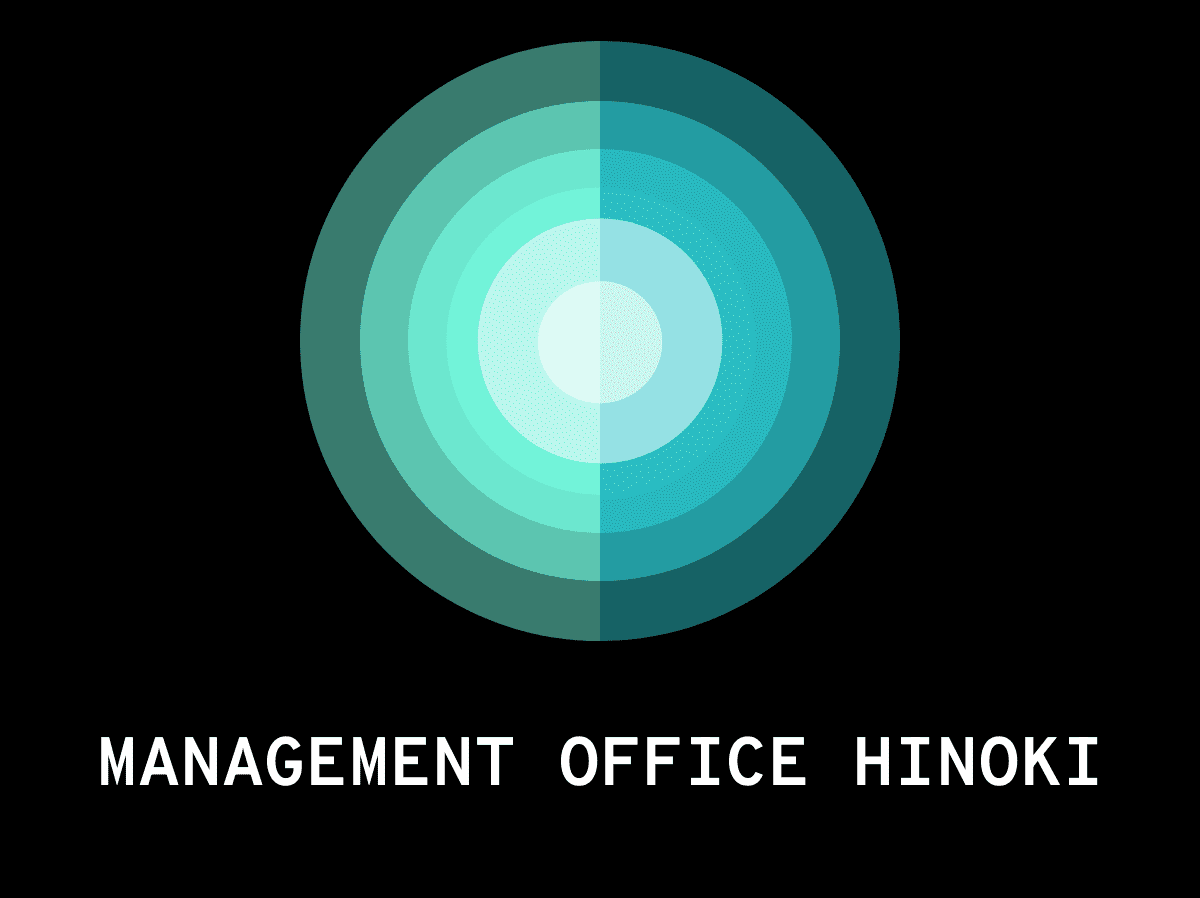みなさん、こんにちは。吉野です。11月も終わりに近づいてきます。みなさん秋はどう過ごしましたか?読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、秋は実りの季節。私は旅をしたり、仕事をしたり、人に会いに行ったりと充実した時間を過ごすことができました。コロナウイルスのパンデミックから今年で3年目ですか?心も体も委縮しがちですが、こんなときこそ旅。写真は旅先で出会った黒猫。かわゆす。

さて、そんな秋ですが、先週所属しているクラブの代表から連絡が。どうやら「近々、世界(金融マーケット、国際情勢などすべて含)が大きく動くとのこと」。実は何回かこうしたタイミングがあったのです。しかし、様々な事情で遅延、または変更。動くはずの事態は動かず。ようやく時が満ちたということなのかな? それはまぁ、これは大変大した話なのだが、私のように一般庶民が直接どうこうではないので見守ることにしましょう。
それともう1つアナウンスが。「2023年の抱負を考えるならこの週に」とのこと。興味深い。2023年の抱負を立てる時期と聞くとみなさん、いつをイメージします? たいていの場合は、お正月ではないかな。私も大抵はお正月の三が日に建てるパターンが多かったように思います。
ただし、それはあくまで世の中が落ち着いているときの話。一向に収まらないコロナパンデミックに加え、記録的なインフレ(それでも日本はまだ上がり方が緩やか)、世界的な金融引き締め議論などなど事実を並べてみると今って、”乱世”そのもの。こうした状況の中で通常通りの暦通りに生活していると”ショック”が起きた時のダメージは大きくなりやすい。
最近、企業においてもBCP(事業継続計画)の重要性がうたわれていますがそのポイントは、至ってシンプル。「非常事態が起きても、被害を最小限に抑えつつ、すばやくビジネスを再開できるように計画を立ててね」という話。(参考:BCPとは?)なにもこれは企業の事業活動に限らず、人生においても同じ。
VUCAと呼ばれるほど不確かな時代を私たちは生きています。
“VUCAとは?予測困難な時代に求められるスキルと、組織づくりのポイント”
今までと同じリズムで過ごしていると、あっと言う間に置いてけぼりどころか生命の危機に瀕する事態にもなりかねない。こうした時代においても健やかに過ごすためには今まで以上にスピーディーな意思決定が求められています。来年2023年、もし、のんびりとした正月が来ないとしたら、、、どうします?
今考えられる時間の中で、スピーディーに意思決定をしましょう。2023年の抱負は2022年の間でも立てることができる。雑に考えるのは避けたいが、悩みすぎるのはよくない。2023年何が起きても悔いが残らないように2023年の抱負は今から立てましょう。
さて、ちなみに抱負や目標を立てる上での注意点はなんでしょう? 〇〇をしたい、〇〇になりたい、こうした抱負はよく見かけます。ただし、叶うのとかなわないものどちらが多いかと考えると、圧倒的に後者。願いをかなえるためにはちょっとした工夫が必要です。
まずもって、ワナビー思考から脱すること、これがポイント。というか私の経験上(笑) かなわない目標なんて山ほどありましたからねぇ(笑) ちなみにワナビーとはどういうことか?
ワナビー とは、 英語の「want to be(…になりたい)」を短縮した口語表現 で、 何かに憧れ、それになりたがっている者 という意味です。 ワナビーの語源は、英語の「want to be(…になりたい)」で、それを短縮した表現である口語表現の「wanna be」をもとにしています。 有名人や人気者などに強くあこがれ、それになりたがる人をさします。 多くの場合、あこがれてまねをするけれど、実質が伴わない人のことをいいます。
出典:コトワカ kotowaka.com/young/wannabe/
動機としての憧れは構わないが、抱負としての憧れはかないません。なぜなら、憧れという思考には「中身」がないからです。中身がないものを投射しても中身がないものが映し出されるのみ。憧れは文字通り、好きなアーティストのLIVEを観客席から眺めている状況となります。仮にその本人がいつかそうしたステージに立ちたいなぁと思っていても、その状態のみでステージに上がることはありません。
夢を叶えるのは誰でしょう?誰かが叶えてくれるか?たいていの場合はあなた以外の誰かがあなたの夢を叶えるのは難しい。憧れ、ワナビー思考には当事者意識が往々にしてありません。中身がないから当然と言えば当然。たとえるなら、Twitterのタイムラインに現れる膨大な刹那的なツイートか?
では、抱負をあなたの人生に出現させるためにはどうしたらよいか?それは「中身」を入れてあげることです。「中身」とはすなわち、「行動」「日々の思考」「言動」が伴っている状態を指します。抱負を形するためにはたてた後に「行動」「日々の思考」「言動」が一致しているのが求められます。
抱負や目標は何もその場限りの一発芸的なものではない。あくまではじまりです。そこかたまた1年に向けた旅路が広がるのです。その繰り返しが一生。うまくいかなくても、今まで願いがかなったことがなくても大丈夫です。道は変えられます。ただ、受け身の人生では期待することは起きないでしょう。だから、もし、人生を変えたい、今の状況を変えたいと思ったら、2023年の人生を早めに仕込んでおきましょう(笑)仕込んでないとあなたの2023年は、いやあなたの人生が始まらないかもしれない。。。世にも奇妙な物語(笑)
さぁ、2023年すばらしい1年にしましょう。私もがんばります。