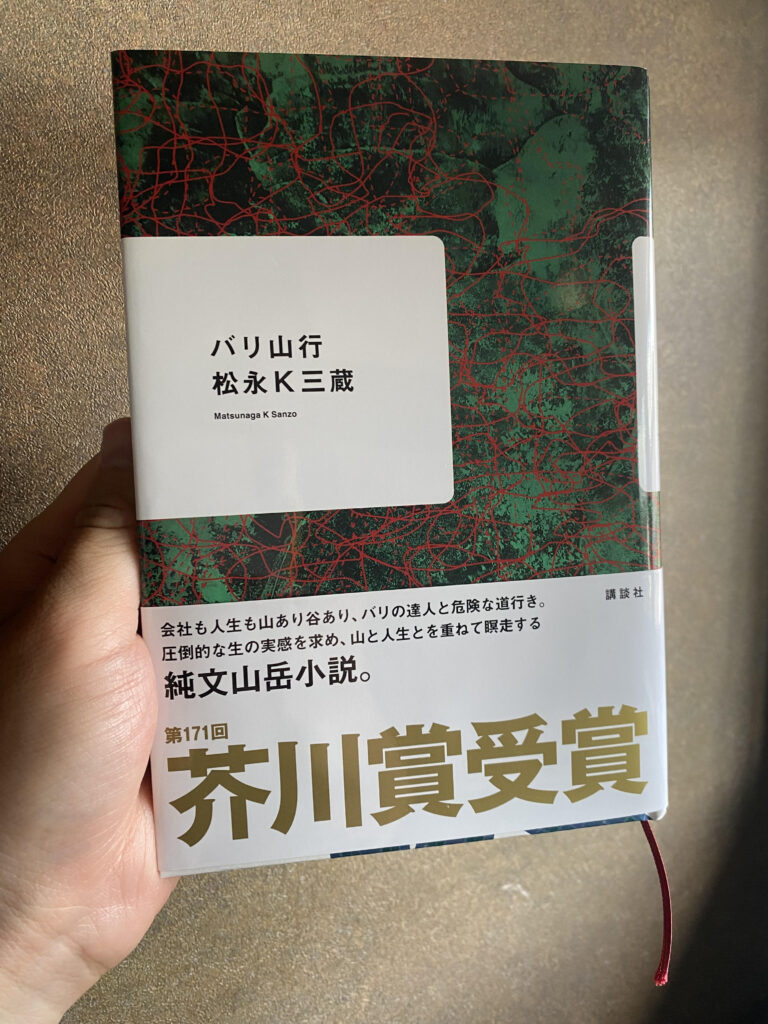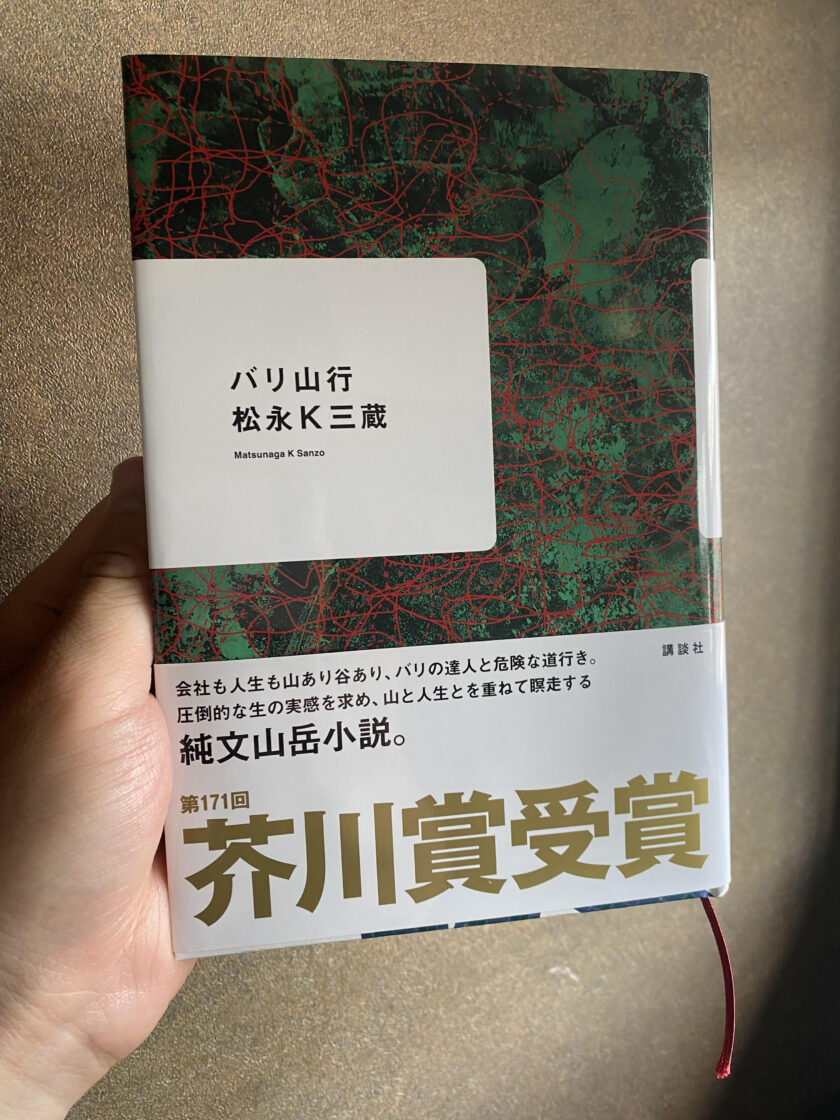こんにちは。さて、暑い夏です。世間を眺めると、株価も暴落があったり、台風も来たりで騒がしい。そんな時は読書に尽きる。ということで、書店へ。普段は古典であったり、経済ジャンルの著作や少年・青年漫画を中心に読んでいる私。この日は、珍しく、純文学の作品をチョイス。第171回芥川賞受賞した松永K三蔵さん著の「バリ山行」。本の帯にあったセリフがなかなかパンチラインで、興味が湧いた。そのセリフはこんな感じ。
「山は遊びですよ。遊びで死んだら意味ないじゃないですか!本物の危機は山じゃないですよ。街ですよ!生活ですよ。妻鹿さんはそれから逃げてるだけじゃないですか!」
バリ山行 松永三K蔵 著
仕事のリフレッシュのために行くハイキングやトレッキングが舞台の小説ではこうしたセリフは出てこない。何やらのっぴきならない雰囲気。帯を見ると山岳小説とも書いているが、面白そう、と思って手に取った。
さて、肝心の内容だが、ネタバレしない程度に言うと、山岳小説の要素:それ以外の要素=7:3くらいの小説となっている。山岳小説というと、ちょっと取っつきづらいが、とても読みやすい。たまに専門用語も出てくるが、スマートフォン片手に検索しながら読めば解決。主人公は会社勤めのサラリーマンさん。そして、第二の主人公というべき妻鹿さんを軸に物語は進んでいきます。ハッピーエンドという感じの話ではないが、バッドエンドという結末でもありません。
山、というかバリ山行の魅力に取りつかれた妻鹿さん、ひょんなことから山登りをはじめた主人公・波多さん。山登りをきっかけに今まで自分が知らない世界を楽しみ、バリ山行(バリエーションルート:一般的な登山ルートではなく、自分の経験と感覚で道標やマーキングなどを見つけて登山するやり方)にも参加することに。同時に会社の状況も変わり。。。
という感じ。山の素晴らしさというより、山というどんな感情もどんな人も飲み込む非日常要素が強い空間とそこに集う人々の底知れない感情の深さやややこしさを感じた作品だった。思えば、私も東京の企業に勤務していたときに、山に登りたくなったことがある。仕事がうまくいかないときほど、それを忘れたいために山に行きたくなるという心理。それで何が解決するわけではないのだが、登って、汗を流して山に飲まれたいという衝動は仕事で行き詰まりを感じる社会人ほどこうした行動は共感するのではないかな?
山登りは命にかかわることが多い。著作中でいうところの生命の危機を感じる場面が多い。崖とか滑落とか危ないよね。雪崩もあるし。それに比べれば、日々の仕事は直接生命の危機を感じる場面は、一部職業を除けば、多くはない。その代わり、仕事をなくしたときのストレスや先行きの見えない不安などを抱えた際のダメージは想像以上に重い。場合によっては心身を病むケースも少なくない。山にある危機よりもある意味重い気がする。山は底知れぬ怖さを持つ存在であるが、それ以上に今はこの社会のシステムそのものが山すらも飲み込んでしまうほどの複雑怪奇な場になってしまったのかな?そんなことも思いました。
もしそうだとすると、自分一人で決断し行動することができる「山」という場所はある意味で避難施設みたいなもんかもしれない。山ガールとかが数年前から流行っていることは社会のシステムに病む人たちが人知れず増えていることも影響しているのも知れない。
ただ、山はきっと答えはくれない。薬も与えない。邪魔もしない。ただ、たたずんでいるだけ。正解も不正解もない。世の中がめんどくさくなればなるほど。山に魅せられる人が増えていきそうな気がする。正解不世界はないし、あなた次第って観点で見ると山は人生みたいだな。バリ山行に目印はないけど、人生にもないもんな。人生山あり、谷ありとはよくいったものだ。ハイカーとすれ違っても基本は孤独だもんな。山は不思議な存在だ。人生も不思議に満ちている。そんなことを感じました。ぜひ読んでみてください。