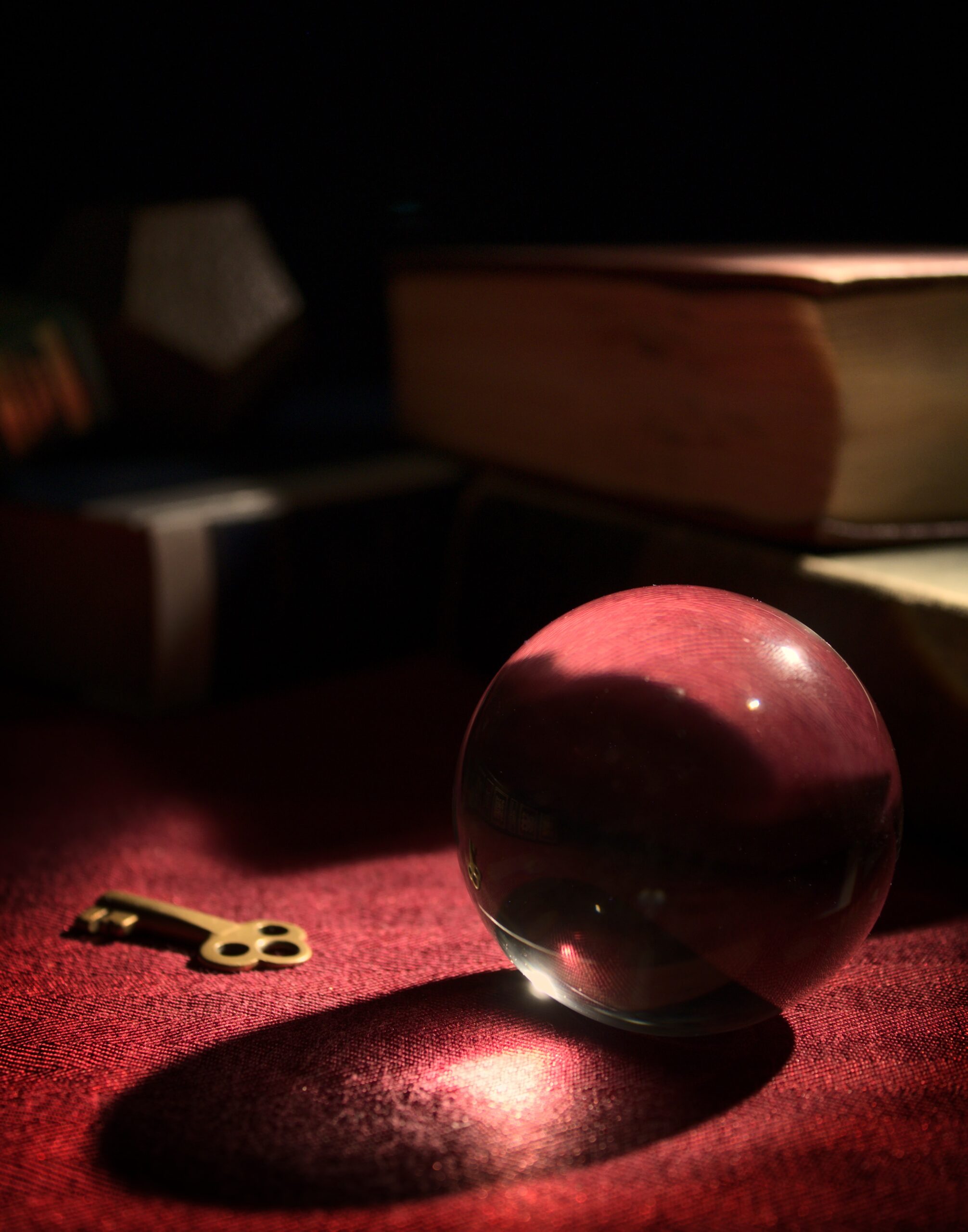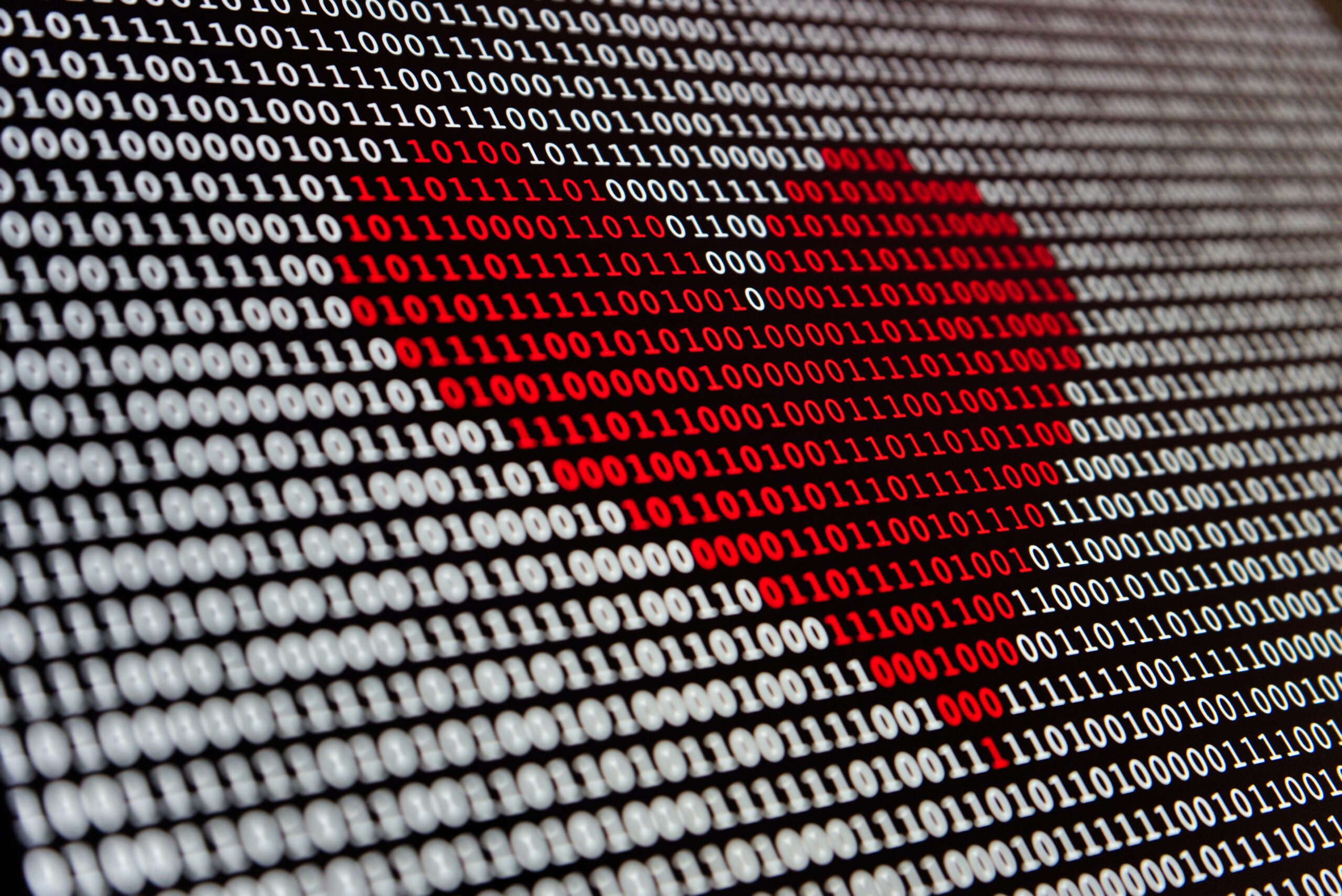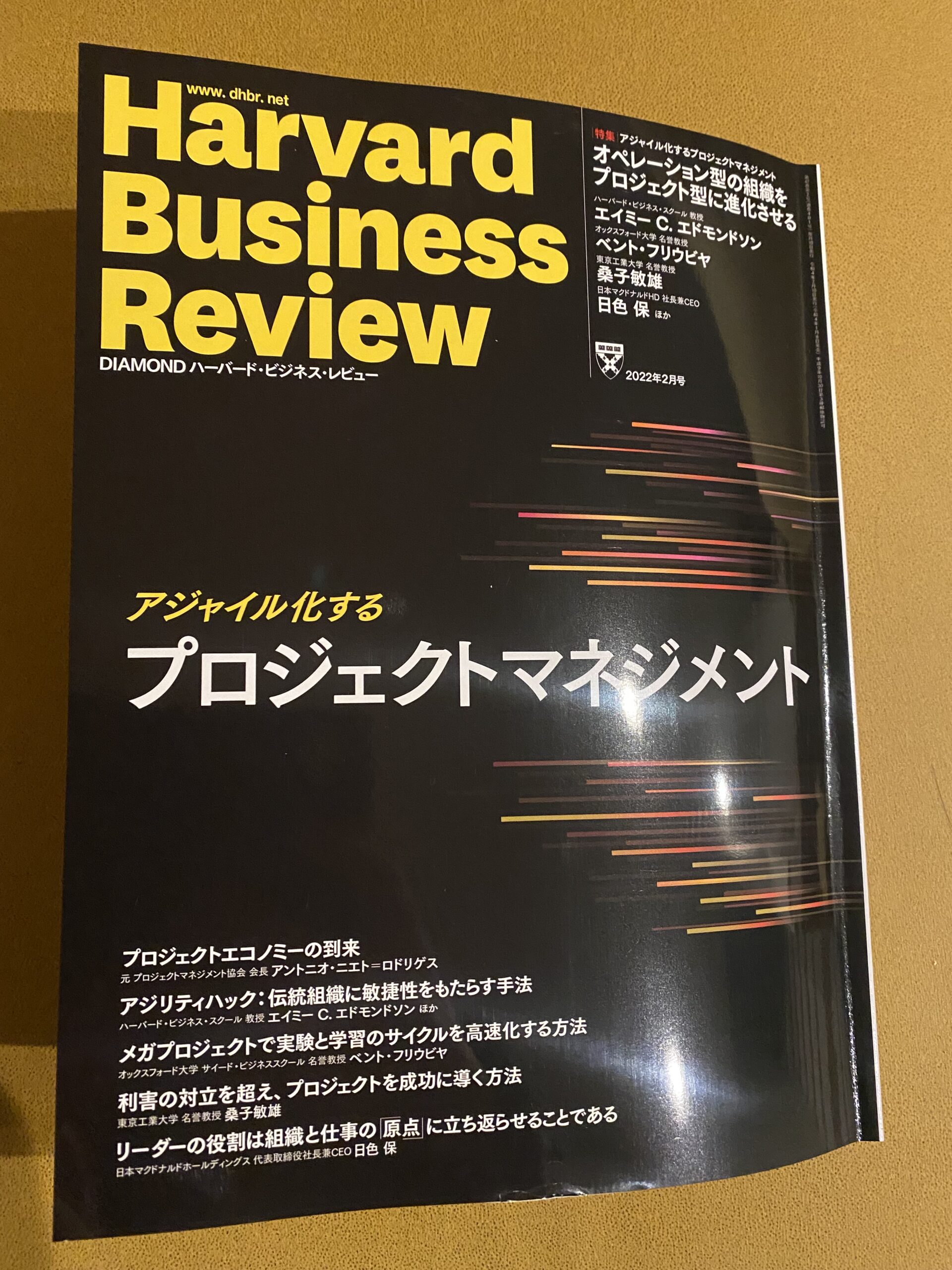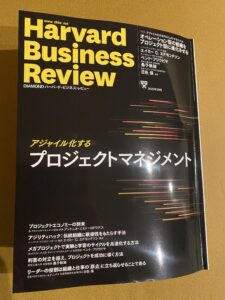こんにちは。皆さんがもしマーケティングに興味があって、ゼロから学ぶとしたらどうやって学びますか?色々な選択肢がありますが、もしかするとマッチングアプリの自己紹介文を教材にして学ぶのよいかもしれません。
そもそもマッチングアプリとは何か?
マッチングアプリは、出会いを求める男女を結びつけるアプリです。
https://woman.mynavi.jp/article/210721-5/
シンプルな定義ですね。出会いを求める男女を結びつけるアプリ。このマッチングアプリなる存在は、4、5年前から徐々に増えはじめた記憶がある。そして、人と会うことに制限がかかりやすくなっったコロナ禍以降一気に市民権を得ましたね。実際、25歳以上40歳未満で結婚活動をしている独身女性の約70パーセントが、婚活で「マッチングアプリ」を使用しているというデータもあります。
【調査】独身女性のリアルな婚活事情 婚活は「マッチングアプリを利用」72.1%! プロが教える“初デートで必ず確認してほしい「3つの感覚」”
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000092251.html
マッチングアプリの中では実際にどんな活動が繰り広げられているか?おそらく、結婚したい男女が、自身の好みにあった人にメッセージなどを送りあい、リモートまたはリアルのデートを複数回経て結婚を目指す、というパターンなのではないでしょうか?
当然ですが、このマッチングアプリを使用している人はたくさんいるので、気に入った異性が現れたとしても相当の確率でライバルと戦うことになります。私の印象では、婚活アプリの戦いはクライアントに対するプロポーザル合戦と似ている気がします。大体似ていますよね。チーム提案ができない、提案期限がない、など異なっている点はありますが。。。
では、このマッチングアプリを通してどうやってマーケティングを学ぶか?何が学べるのか?私の印象としては、マッチングアプリの自己紹介文を通して、ゼロ接点の他人をお客様にするコツを学べるはずだ、と見込んでいます。例えば、こんな自己紹介文があったとしましょう。以下、マッチングアプリの自己紹介文について述べた記事から引用です(記事も面白いので読んでみてください)
例①【たか】さん
https://president.jp/articles/-/53852?page=2(「人気俳優を2発殴ったような顔です」婚活アプリの自己紹介で勝ち組が使っている”最初の60字”「ゲーム」の勝利条件を考えるべき)
はじめまして。プロフィールを見ていただきありがとうございます。板橋区に住んでいる35歳で、仕事は営業をしています。今まで…
例②【まつたろう】さん
https://president.jp/articles/-/53852?page=2(「人気俳優を2発殴ったような顔です」婚活アプリの自己紹介で勝ち組が使っている”最初の60字”「ゲーム」の勝利条件を考えるべき)
はじめまして! 大学で地元山梨県から上京し、現在は学芸大学近く住みです。実家にウサギいます♪ あるTシャツサイトのモデルをし…
例③【ひろ】さん
https://president.jp/articles/-/53852?page=2(「人気俳優を2発殴ったような顔です」婚活アプリの自己紹介で勝ち組が使っている”最初の60字”「ゲーム」の勝利条件を考えるべき)
プロフィールを見て頂きありがとうございます。職場や日常で出会いが少なく、真剣に結婚を考えて思い切って登録しました。仕事…
みなさんが例えば、この3人の男性の中からひとりプロフィールにいいね!を押さなければならない、としましょう。どの男性を選びますか? いろんな考えがあると思いますが、2番目の【まつたろう】さんを選ぶ人が多いのではないでしょうか?なぜ選んだか?その理由も考えてみましょう。
私の分析はこうです。「具体性があり、且つ広がりがある情報なので、興味の壁を突破しやすいから」。マーケティング活動は、いわば「売りたいものを、売りたい値段で買いたい人に買ってもらうための創意工夫」と訳せます。当然ですが、購買意欲ゼロから実際の購買に至るまでの人の心の動きは思ったよりも複雑です。個人的に非常に尊敬している現役のマーケティングコンサルタント、佐藤義典さんが考案した”マインドフロー”を活用し見てみましょう。
認知→興味→比較→行動→利用→購買→愛着
ストラテジー&タクティクスの戦略ツール
マインドフロー http://www.sandt.co.jp/mindflow.htm
つまり、【まつたろう】さんのプロフィールは、認知、興味、比較の壁を一気に突破したと言えるのです。実際、彼がここから意中の相手と結婚できるかは分かりませんが、少なくとも結婚に至るまでの道のりを前進させることができているのです。今回の例はマッチングアプリですが、これってビジネスでも同じじゃありませんか?
あえて、ビジネス的な現場に今回のケースから結論を導き出すとしたらこんな感じでしょう。「無難な情報は捨てる。届けたいお客さんを惹きつける情報を強調する」例えば、温泉旅館があったとしたら、温泉がウリです。とか美味しい料理が自慢です。などの情報は語らない方がいいでしょうね。もし、その旅館に芸能人が多く訪れるのであれば芸能人御用達の一言でイイじゃないですか。こうした訓練を繰り返すと、必然的に広告やHPに書く文章も洗練されてきます。私の場合はこんな感じかな?
ゼロから始めた創業者さんと相性がよいコンサル。広告宣伝費は増やしません。御社の事情を深く考慮した売上アップの作戦を企画し経営者と一緒になって実行。社外マーケティング役員(CMO)実績あり。
ビジネスにおいても、婚活においても万人受けする必要ありません。伝えたい人に伝わればイイのです。なので、もし、あなたが今年マーケティングを実行して自社の売り上げを伸ばしたいなら、無難な言葉を並べるのはやめましょう。具体的かつお店のウリをもっと伝えましょう。アイディアに煮詰まったらマッチングアプリの自己紹介文を眺めるのもいいかもしれません。今回の記事を書いて思ったのですが、マッチングアプリや婚活サイトに登録したが、成果がでない人向けのコンサルティングはできるかもしれませんね。ご興味ある方はぜひ。お読みいただきありがとうございました。