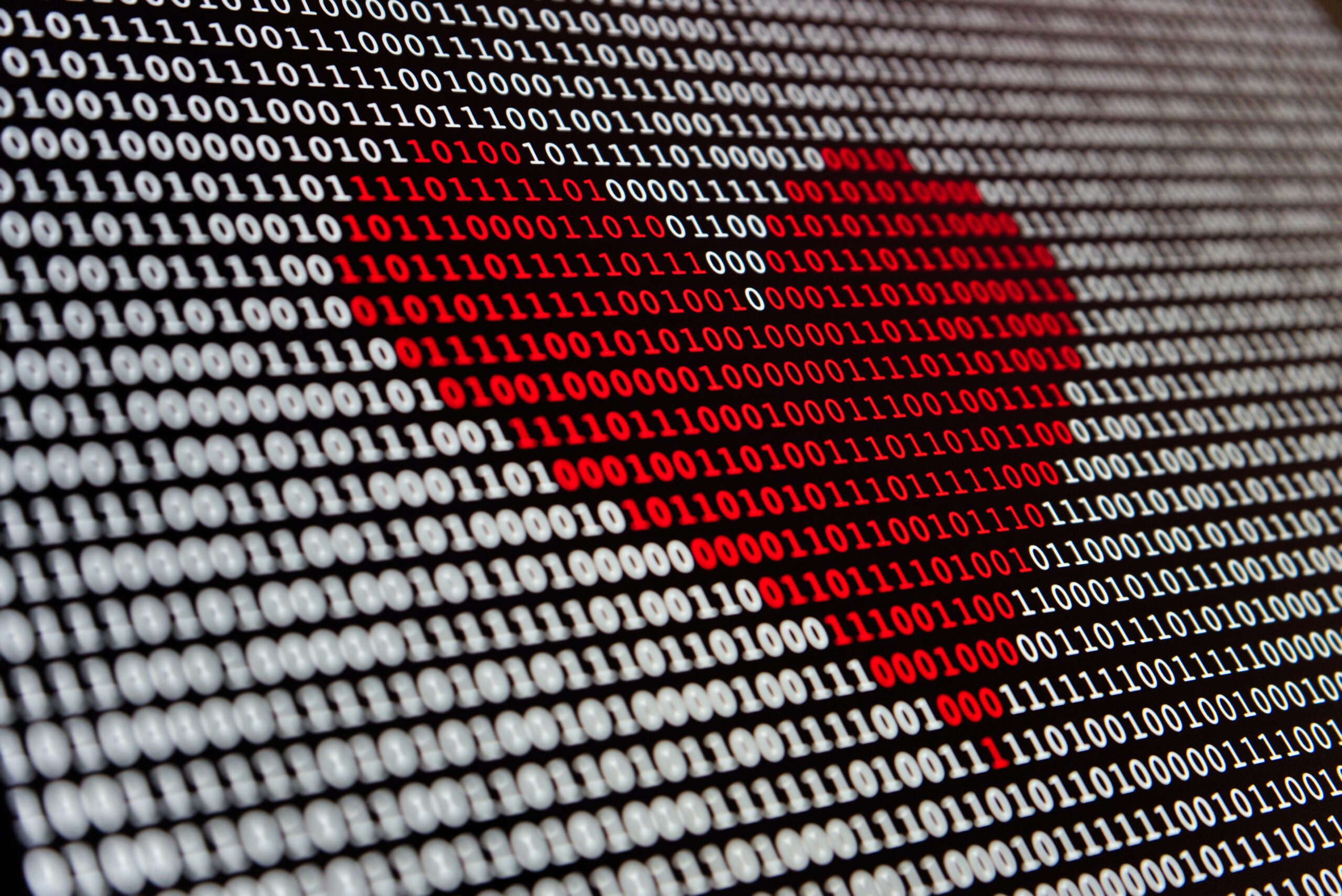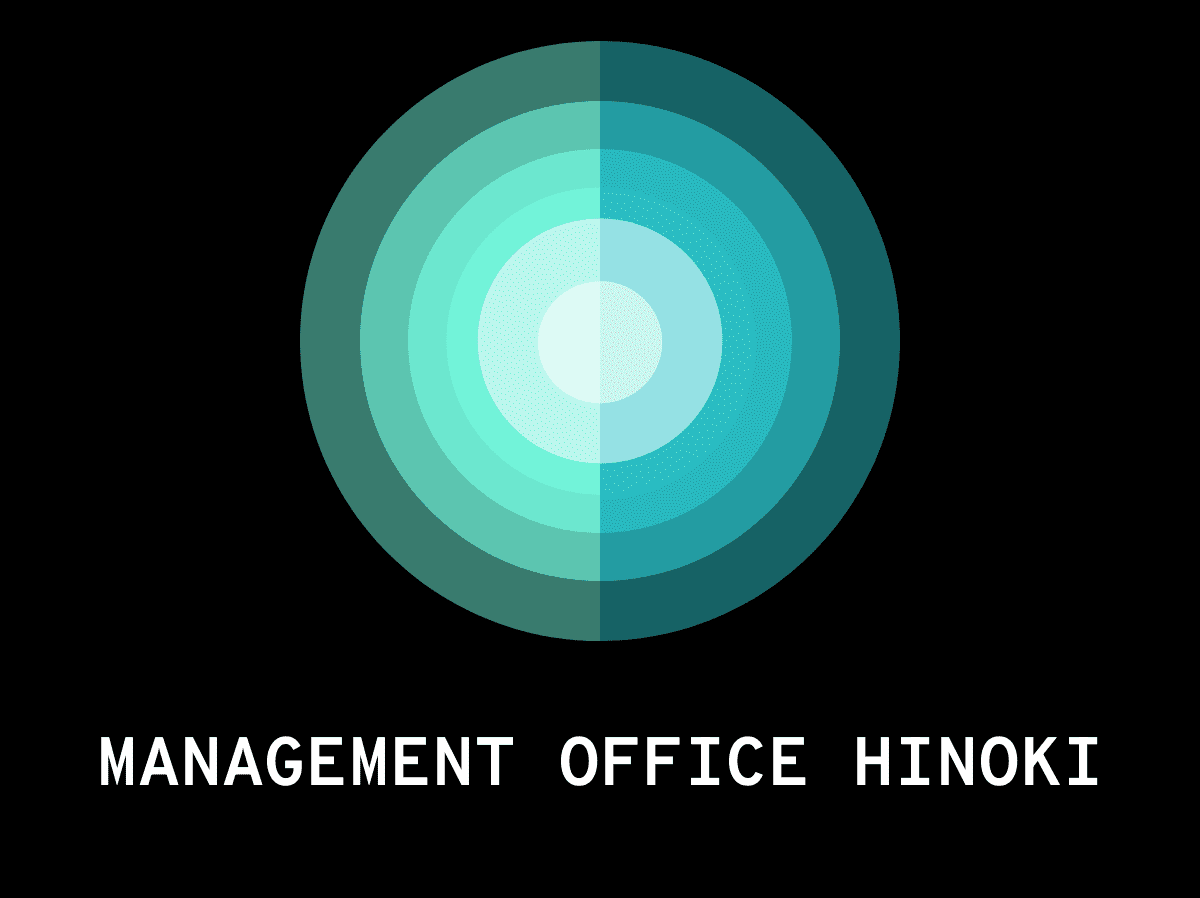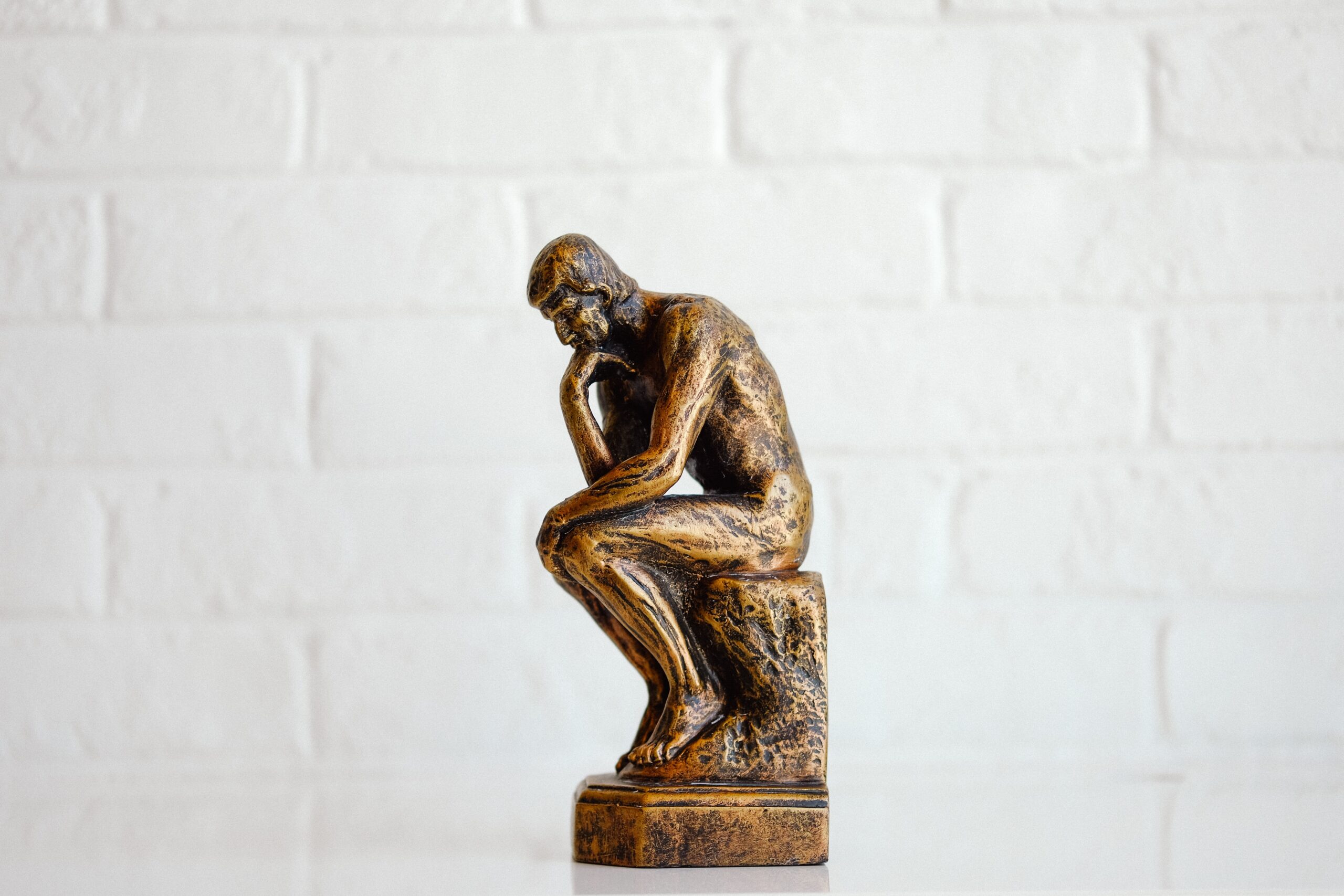こんにちは。あっという間に12月!早いですね。今年やり残したことはないか?日々自分に問う日々を慌ただしく過ごしています。みなさんはどうですか?私はまだまだ今年にやりたことがあります。全部終わるかは私次第😎 がんばろう。
さて、表題の件。今の日本経済が置かれている状況というのはとても厳しい。インフレ止まりませんし、賃金は上がらない。そして、電気料金高騰。一部の富裕層(純金融資産1億円以上)を除けばこの状況でマイナス影響を受けている人の方が多い。そして、来年以降日銀がついに金利を上げるか?とも言われている。利上げの影響は当然住宅ローンにも波及。
今後10年以内に住宅ローン金利は上がる? 10年固定金利への対応から、銀行ごとの金利予想を分析(ダイヤモンド不動産研究所)
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/1111740
これ以上、景気が悪くならないでぇ〜!と叫びたくなりますが、おそらく来年もインフレ傾向は続きますし、賃金上昇もあまり期待できないでしょう。それは悲観的なシナリオではなく現実的な予想なのでしょうがない😊
大事なのはここから。では、どうしよう?まずポイントは、どんなに経済状況が悪くなったとしても、日本経済、いや日本社会そのものがスイッチオフみたいに一瞬でリセットされる事態はあまり想定できません。たとえ、日経平均や日本国債が暴落しようが、社会騒動がたくさん起ころうが、全てがゼロになるということはない。この辺のリアリティは、真山仁さんのオペレーションZが近い気がします。
連続ドラマW オペレーションZ ~日本破滅、待ったなし~ DVD-BOX
https://www.tc-ent.co.jp/products/detail/TCED-5401
つまり、世界はいきなりなくなりませんし、生活は続きます。ということは、”時代の流れ”を意識し、どのマーケットに活路があるのか?どういう方向性に世界が変わっているのか?を意識しながら上手に適応していくことが求められます。
では、その際はまず何から始めたら良いか?まずは国の各省庁が取りまとめている中長期的な経済政策を眺めてみることから始めましょう。未来を完全に予測することは難しいですが、ある程度輪郭を掴むことはできます。その際、参考になるのは意外に”お堅い”レポートだったりします。たとえば、岸田政権が掲げた”新しい資本主義”の中身、みなさんご存知ですか?こうした資料も眺めてみることで、今後国がどういう分野に力を入れていくか?が理解することができるのです。政権を支持する、支持しないという気持ちは一旦クリアにして、日本の中枢が何を考えているかを冷静に見極めるのです。
政府広報オンラインサイト(新しい資本主義の実現に向けて)
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/newcapitalism/
ちなみに、新しい資本主義で中心になる4分野は次の通りです。
■人
■科学技術・イノベーション
■スタートアップ
■グリーン・デジタル
このサイトがわかりやすい。
NHK政治マガジン 「新しい資本主義」で「資産所得倍増プラン」分配戦略後退指摘も
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/83913.html
抽象的な表現が多い気がしますが、政府関連の資料を読み込んでいくと、具体的な分野がしっかりと浮かび上がってきます。例えば、4つの分野の中にある”グリーン”というワード。これはグリーントランスフォーメーション(GX)に力を入れていくことを指しています。このグリーントランスフォーメーションというワードの中には、半導体、風力発電、EV、データセンターなどの具体的な分野が含まれています。
2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html
そういえば、次世代半導体を扱う会社を大企業が協力して立ち上げましたね。こうした取り組みのもとになっているのは国が定めている大きな戦略です。
新会社「ラピダス」始動、次世代半導体の国産化へ一歩 10年近い遅れを得意のものづくりで挽回
https://www.netdenjd.com/articles/-/276111
なぜ、こうした情報がこれから重要になるかというと、「国」が予算を出すというマーケットには、成長のチャンスがまだまだあるからです。良いか悪いかはさておき、国が予算を出すいわゆる”官製マーケット”は底堅い。仮に政府がなくなったとしても、大きな方向性は変わらず、次の政府も同じような方向性を向いていくでしょう。(例えば、デジタル化やDXというキーワードは政権がどこになろうと世界的な潮流なのできっと実施する方向で変わらないはず)
景況感の改善があまり期待できず、内需や外需を中心にしたマーケットも盛り上がりにかけることが予想される来年以降の日本経済(景況感とは関係なく金融マーケットの盛り上がりなどは期待できます)。それでも事業者は事業を続けていきますし、われわれ庶民の暮らしも続きます。たとえ、どんな状況になったとしても。。。
こうした状況下で頼りになるのは何か?金融資産もインフレ下ではあまりにあてになりません(目減りしていくので)。ましてや組織や団体に人生を委ねることはこの不安定な時代においてかなり危険。ではどうするか?1つ考えられるのは、デバイスや人的ネットワークを駆使して、世界と日本の大きな「流れ」を捉え、その流れにそって生き方や仕事を合わせていく柔軟なセンスを磨くこと、です。
住んでいる場所も現時点での年収も、今までの過去の実績もこの変化の激しすぎる時代においてはあまり意味をなしません。どこにいても、何歳であろうと、主体的に世界と対峙し、自分の人生の舵を切っていくのです。情報と自分の人生がコネクトするスピードがこの3年で加速度的に増しました。世界の状況と無関係でいられる「安全地帯」はもはや国内外どこにもないでしょう、少なくとも一般庶民レベルでは(王族は別)
自分のキャリアを考える際は、自分のやりたいことも大事なのですが、それに加えて、今後は必ず、大きな世界や日本が向かっている方向性をおさえるようにしてください。景況感の改善は多分しばらく期待できません。
つまり、予算がつく分野や成長の余地がある分野はすでに決まっている。いずれはAIの劇的発展によって将来は働かなくても大丈な状態になると思いますがそれはもうちょっと先でしょう(そうした未来に関してイメージを深めるためにはこの本がおすすめ:https://www.amazon.co.jp/財政破産からAI産業革命へ-日本経済、これから10年のビッグ・シフト-吉田-繁治/dp/4569832636/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&crid=TJDB0JDHPX19&keywords=ai+経済+吉田&qid=1670662642&s=books&sprefix=a+i+経済+吉田%2Cstripbooks%2C177&sr=1-1)
大きな流れをおさえて、自分のビジネスや生き方をトランスフォーメーションしていきましょう。DX・CX・GXなどが向かう先は結局のところ、「LIFE TRANSFORMATION(LX)」なのです。生き方を大きく変えていく。LIFE SHIFTという本がベストセラーになったのもこうした背景があるはず。当然、私も例外ではない。変えていく必要がある笑 がんばるぞ!
まとめます、瑣末な情報に決してとらわれず、時代の流れを積極的にキャッチアップしましょう。最初は公開情報を取りに行くことが肝心です。世界の流れ、日本が向かっている大きな方向性を読むのです。そして、そこを意識して、向こう30年程度自分自身のキャリアや人生をどうそこに合わせていくのが戦略を立てていく。時間軸は数ヶ月で終わらず長ければ数十年の長い時間軸になると思います。
それでも先はきっとあるはず。2022年悔いのないように過ごしましょう😊 久しぶりに堅い記事笑 色々書きましたが、幸せを掴むためには日頃の努力が大事だよという話ですね。以上です。