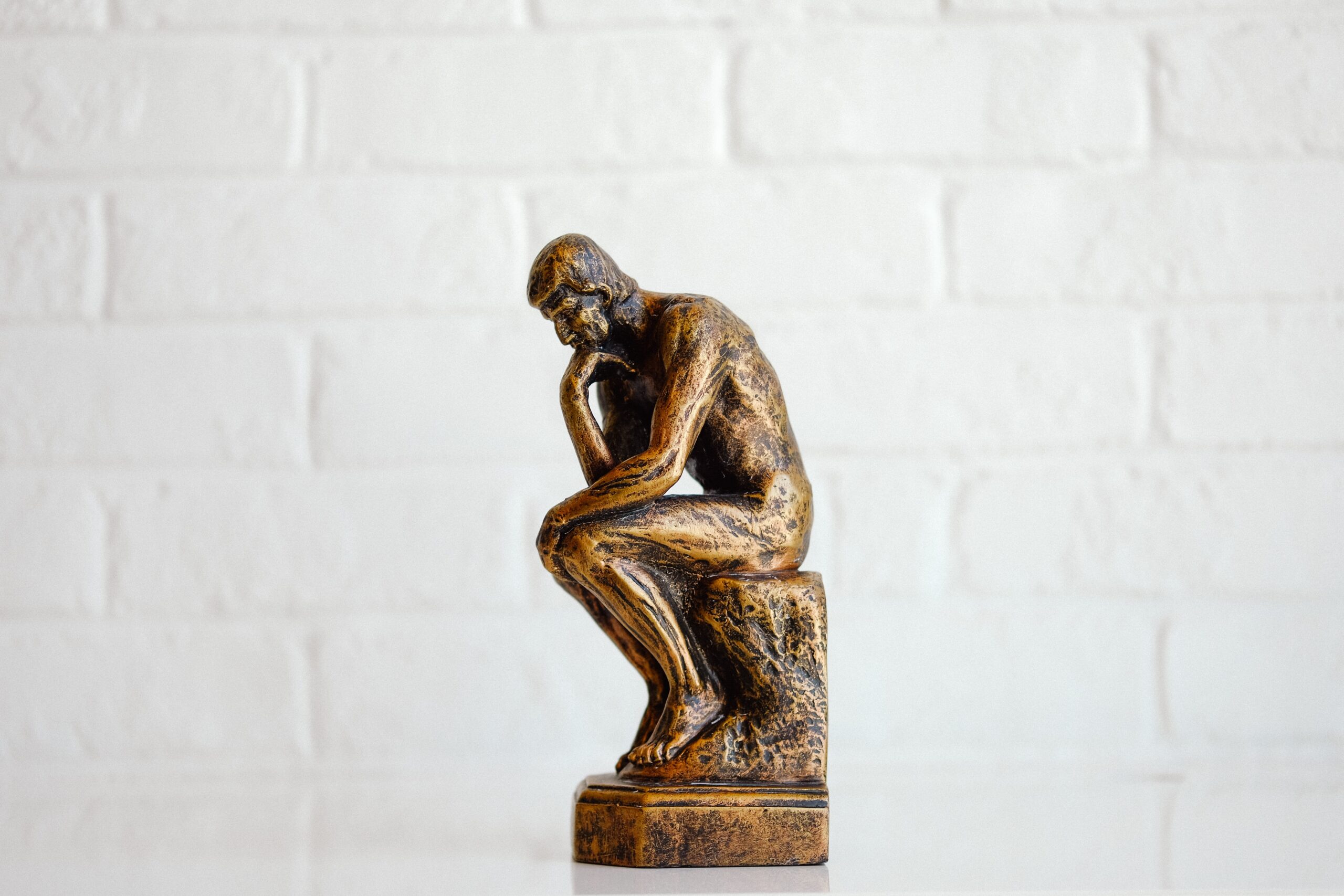おはようございます。7月2日(土)自宅にて寛いでいます。6月があっという間に終わり、7月がはじまりました。今年は夏祭りや花火大会など夏のイベントも再開傾向。コロナが始まってから初めての夏らしい夏になりそうです。
さて、日常生活は徐々にコロナ禍からの「明け」が見えてきたわけですが、「明け」の景色は当初の想像とどうやら異なっているようです。「明け」で見えてきた景色はまとめるとこんな感じ。「終わらないコロナ」「加速する物価上昇」「回復のめどが立たない消費者マインド」。こんなはずではなかったという声が聞こえてきそうなワードが並びます。
この中でも一番キツイのは「加速する物価上昇」でしょう。なんといっても全世界的に物価上昇が収まる気配が立っていません。先日、EUが発表した6月の消費者物価指数は前年度同月から8.6%上昇を記録(ちなみにこれは過去最高)
ユーロ圏物価8・6%上昇 過去最高、7月利上げへ
欧州連合(EU)統計局が1日発表したユーロ圏19カ国の6月の消費者物価指数(速報値)は、前年同月から8・6%上昇した。上昇率は5月の8・1%から拡大し、集計データのある1997年以降で過去最高を記録した。欧州中央銀行(ECB)はインフレ抑制のため、7月に11年ぶりの利上げに踏み切る考えだ。
https://www.sankei.com/article/20220701-RRW36F2WYVMLJCYJKS5SNQH4P4/
もちろん、日本もそうです。特に最近上昇が目立つのは電力料金。大手電力会社10社は電気料金を去年に比べて10%から30%値上げをしています。月々10,000円の電気料金であった場合は11,000円から13,000円くらいに上昇している計算に。個人家庭への負担増は今後の景気の先行きに不安が残ります。電力を使う製造業やサービス業のみなさんにとってはまさに死活問題。しかも、収束の気配が立っていないと来たもんだ。食品及び電力の値上げについては秋以降も続く予定(食用油と小麦粉の供給が国債的に滞っていることが原因。ウクライナの件が片付くまでは続くということ)
まだまだ止まらない食品値上げ 年内に1万品目突破の衝撃!
「値上げの夏」と報じたばかりだが、食品の値上げは秋口以降も続く可能性が出ている――。帝国データバンクが2022年6月1日に発表した「『食品主要105社』価格改定動向調査(6月)」でわかった。上場する食品主要メーカー105社を対象とした同調査では、2022年以降の価格改定計画(値上げ、実施済み含む)を追跡調査したところ、5月末までに、累計1万789品目で値上げの計画が判明。実に、半年間で1万品目を超える値上げとなった。
https://www.j-cast.com/kaisha/2022/06/02438521.html?p=all
動乱の時代、というのは過去にもたくさんありましたが、自分が生きている時代がまさにそうなるとは!私は経済の専門家でもなんでもないのですが、全国民が「景気がよくなった!」的な実感を得るような景況感はしばらく訪れないと感じています、むしろインフレの具合は今年、来年とどんどん進行するでしょう。部分的な金融バブルの発生はあるとは思いますが。。。
つまり、こうした事態はしばらく続くことを自分の人生に織り込んでおいた方がよいと私は思います。ではどうすればよいか?資産防衛?移住?転職?結婚?節約?自給自足?それらもやってよいとは思うのですが、それよりも大切なことがある気がします。
それは、「自分の心の平穏を保つこと」。真面目にそう思います。終わらないインフレ、マスクをしても手指消毒をしても消えない感染への不安、よくならない景気、限りない将来への不安。。。外を眺めても希望は見当たりません。バラエティ番組や質の良い映画を観ると少しは気が晴れるかもしれませんが、長続きはしないはず。それよりも自分の人生に集中し、穏やかな気持ちでいれるように静かに過ごしてみてはいかがでしょうか? 最近、あまり聴かなくなりましたが、マインドフルネスという取り組みと似ているかもしれません。マインドフルネスは「心の筋トレ」とも呼ばれるようです。
物価上昇は続きそうですし、それがいつ終わるのかは分かりません笑 また、世界各地で戦争が起こるかもしれませんし、起こらないかもしれない。パンデミックがいつ終わるか?それも分からない。要するに外で起きていることをコントロールすることは不可能なのです。コントロールできないことに自分の心や人生が左右されるのは寂しい気持ちになります。フォーカスすべきは外ではなく、自分の人生です。今、厳しい状態に置かれている方はとても多いと思いますが、そういう時こそ外に目を奪われないようにしてくださいね😊
ちなみに、書いておいてなんですが、私は瞑想はやりません。瞑想がわりに行うのは美味しいコーヒーを淹れること、本を読むこととかです。美味しいコーヒーを淹れて、奥さんとゆっくり飲むときの時間って幸せです。インフレだろうが景況感悪化だろうが幸せです笑 それでいいと思うんですよ。人生って。
皆さんもそんな感じで心おだやかな時間を意識的に作るようにしてみてくださいね。外はしばらくよくなりませんから。こんな時だからこそ静かにご自愛ください💌
追伸)我が家のコーヒー豆は全国各地の喫茶店から気の向くままにお取り寄せしたり、現地購入を行っていますが定番もあります。定番はやはりココ。季節のブレンドいつも大満足です。未体験の方はぜひ。