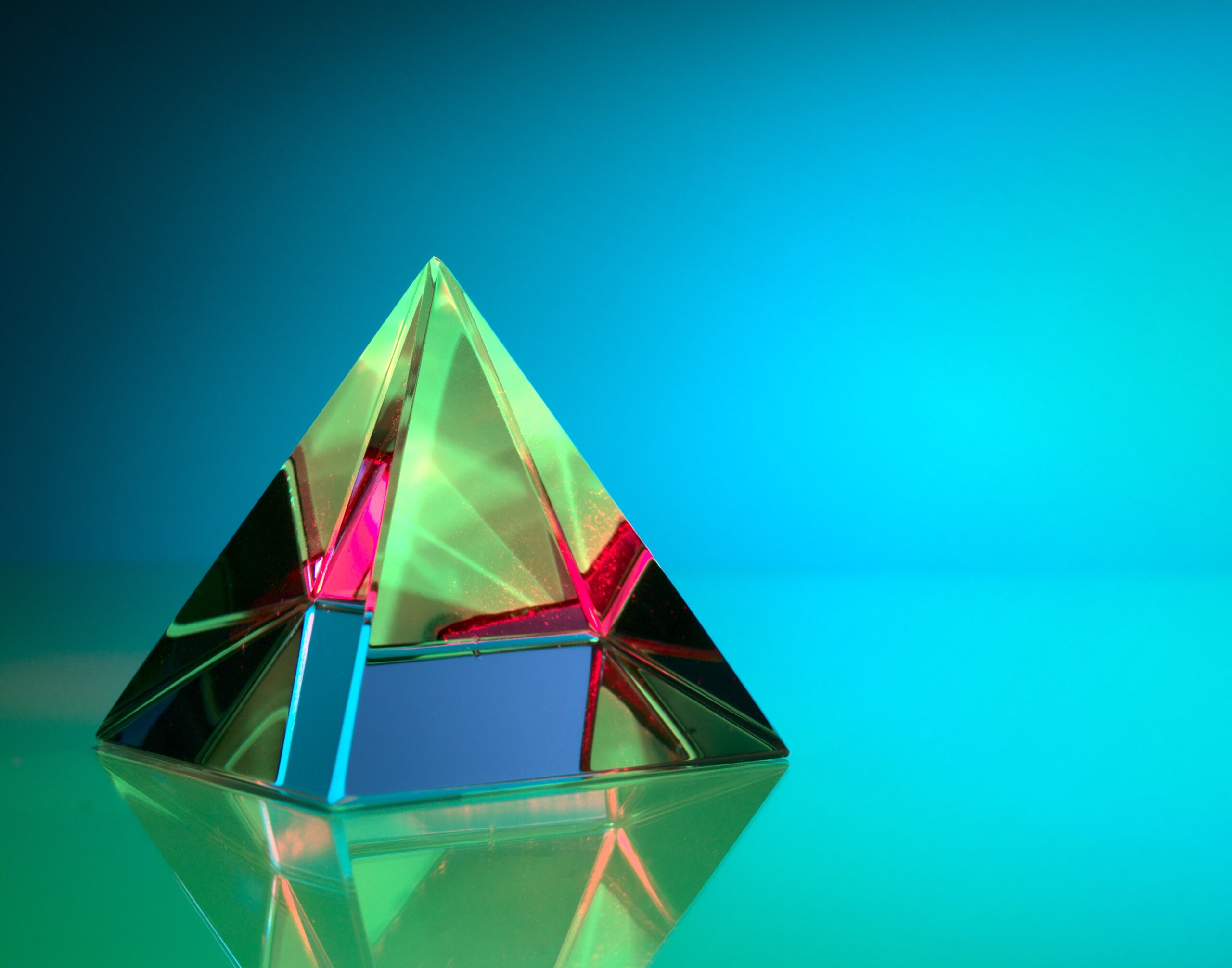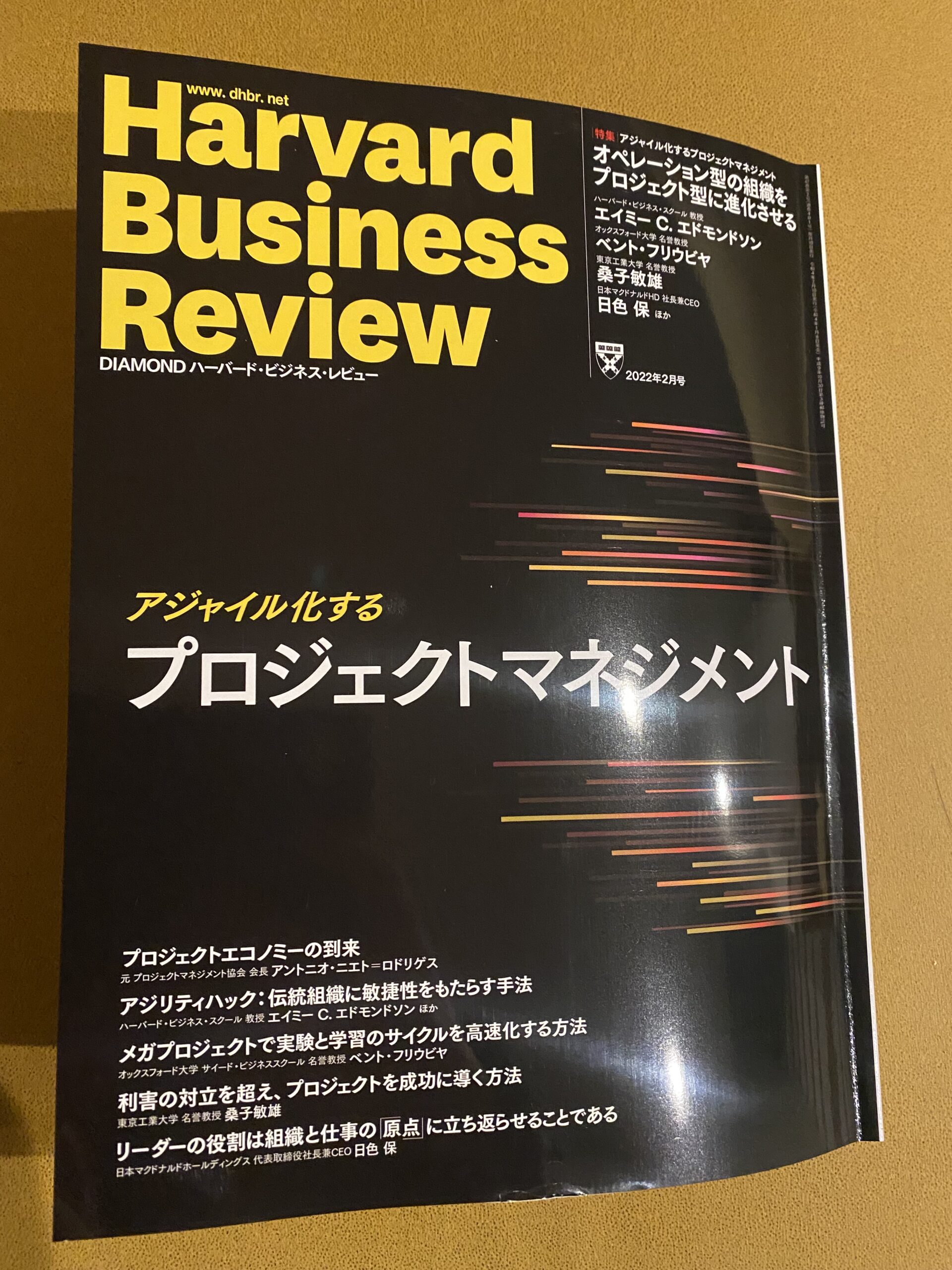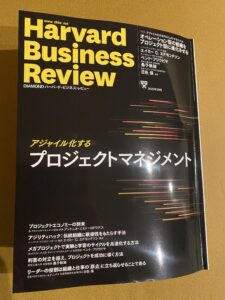こんにちは。さて、毎月読んでいるハーバードビジネスレビュー、今月号も届きました。その中で、とてもためになる記事がありました。記事のタイトルは”「否定的な感情がない」ことが幸福ではない=英題:Happiness Isn’t the Absence of Negative Feelings”。幸福についての論考。とはいっても、堅苦しい内容ではない。以下、ポイントを記事から引用。
「私たちは”幸福であること”を最終的なゴールと見なしがちですが、本当に重要なのはそこに至るプロセスであることを忘れています。何をしている時が一番幸せかを発見し、その活動に定期的に関わることで、私たちは充実した人生を送ることができるのです。」言い換えれば、幸福を追い求めている限りは幸せになれないということだ。幸せになれるのは、幸せになりたいという思いを忘れている時だ。
「否定的な感情がないこと」ことが「幸福」ではない ジェニファー・モス DIAMON ハーバードビジネスレビュー4月号より
非常に示唆的な文章だと思いませんか?これは何も幸福に限ったことだけではない。例えば、お金持ちになりたい、年収○○○万円になりたい、起業して○○になりたい、など。構造的には同じことですね。お金持ちになるのも、年収○○○万円になりたいと掲げるのは自由ですが、その達成と幸せは関連性がないことは冷静に認識しておいてもいいでしょう。お金を稼ぐことと幸せになるのは相関関係はあると思うが、因果関係はないのでは?ここを混同するとエライことになりますよ😊
幸せになりたい、という言葉の裏には、自分の生活・人生と”幸せ”が切り離された状態であることを認めている心理が現れている気がします。幸せがゴールでそこに向かってマラソンしていくようなそんな感じでしょう。もし、あなたがそういう考えを持ちやすければ、”幸せ”とはゴールなのではなく、”幸せ”とはプロセスなのだと認識を改めるといいでしょう。日常の中で自分が充実感を感じられる瞬間、出来事をどんどん取り入れていくのです。それを繰り返すことによって、自分の人生が少しずつ、モノクロ映画がカラー映画になるように徐々にですが、劇的に変わっていきます。
お金がないことが幸せになれない理由なのではない、奥さん旦那さんがいないことが幸せになれない理由なのではない、極端な話、自分が幸せか不幸せかなんて評価は投げ捨てるくらいがちょうどいい。そんな議論を取り入れるくらいなら、心から楽しめる瞬間や充実した瞬間を毎日に探して、少しずつ増やしていきましょう。くれぐれもTVやSNS、友人、知人のストーリーを聞いて、自分にな不足ている条件を探して満たされない気持ちにならないように。。。気をつけましょうね。
あなたが幸せならそれでいい。あなたが元気で毎日イキイキしていればそれでいい。そこには流行りのFIREや年収○○○万円、なんて金銭的な条件が入り込む余地は一切ない。ある意味成功することよりも、幸せになることの方がずっと難しい世の中になってしまったと感じます。さぁ、季節は春です♪爽やかな気持ちで毎日幸せに過ごしましょうね😊 がんばるあなたに詩を贈ろう。
「ことばが信じられない日は、
窓を開ける。それから、
外にむかって、静かに息をととのえ、
齢の数だけ、深呼吸をする。
ゆっくり、まじないをかけるように。
そうして、目を閉じる。
十二数えて、目を開ける。すると、
すべてが、みずみずしく変わっている」
長田弘『世界はうつくしいと』より