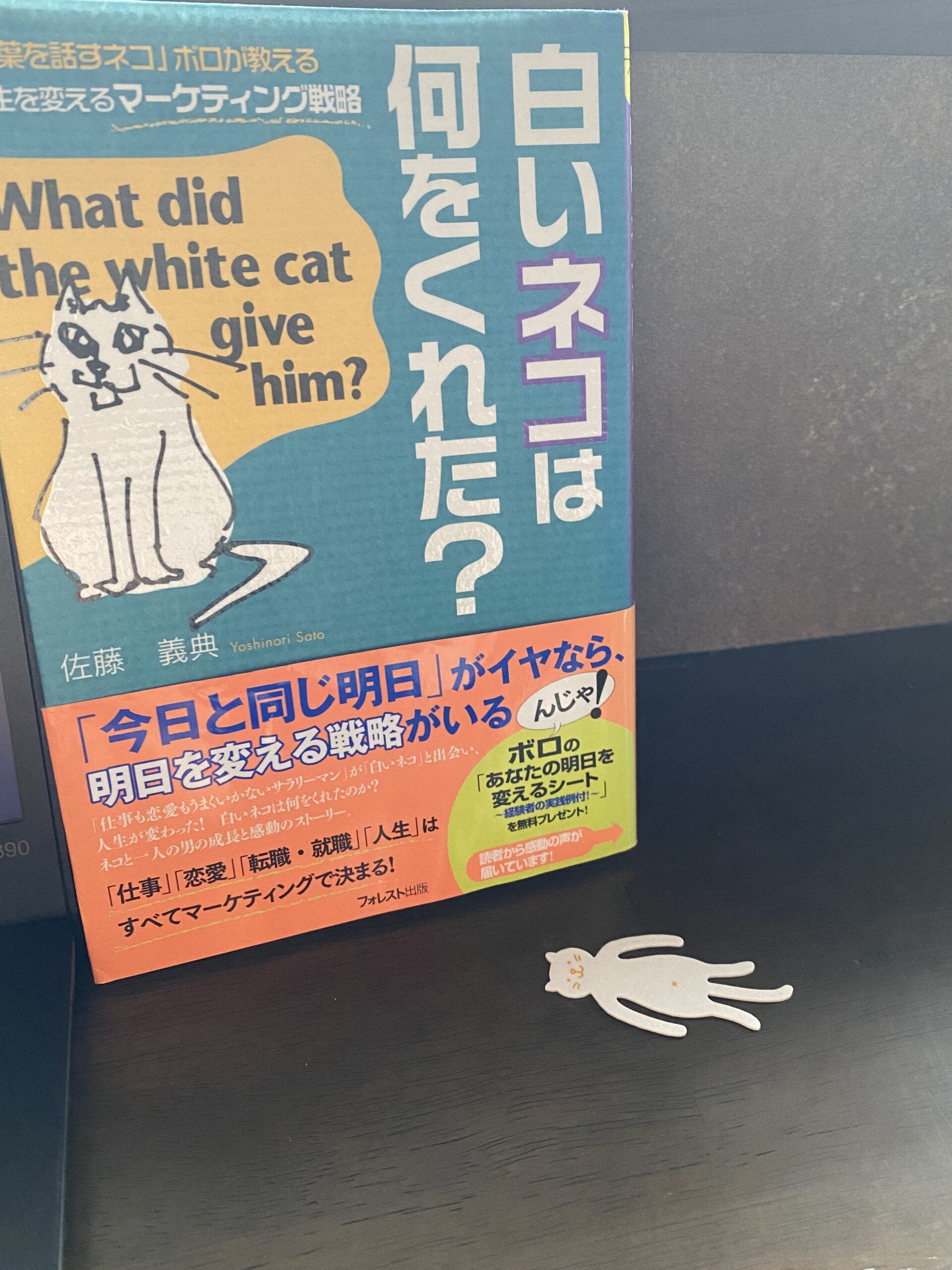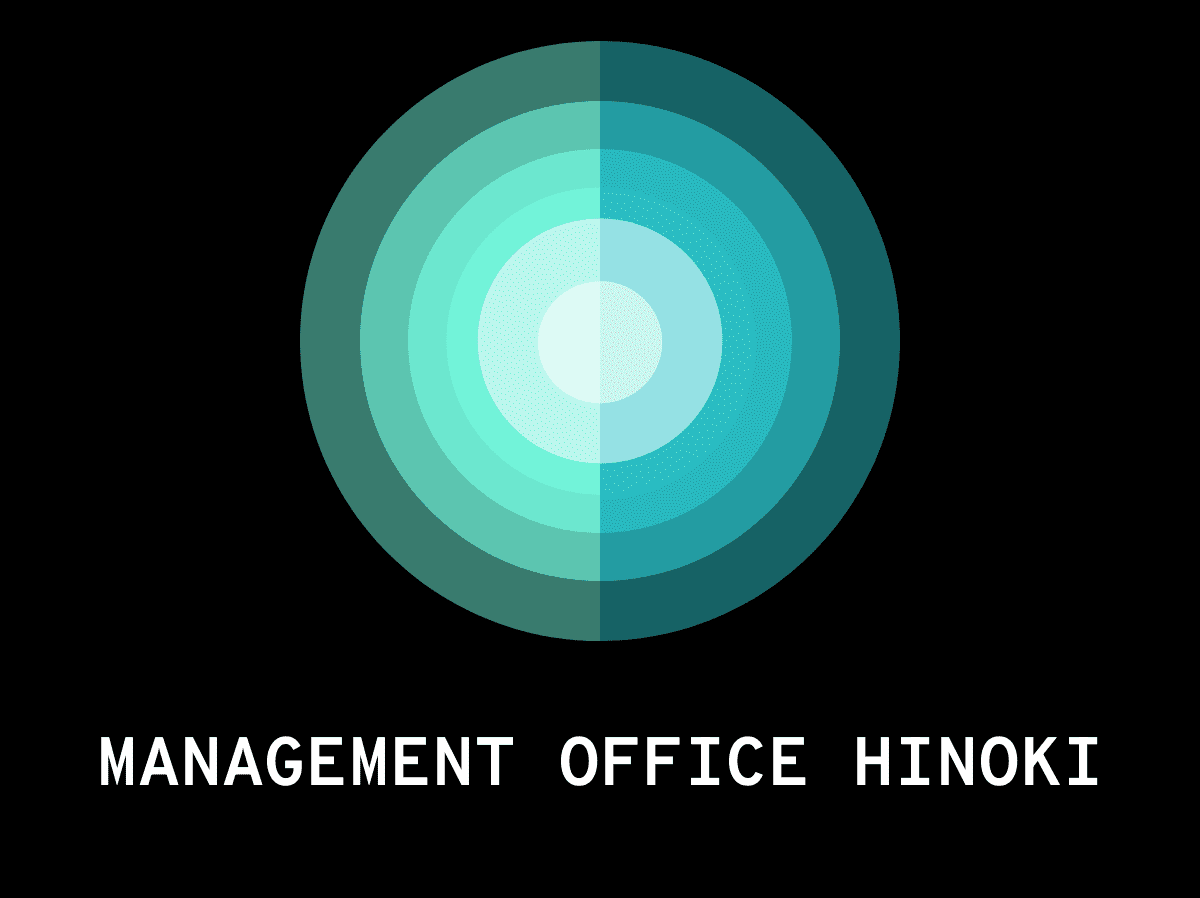こんにちは。マネジメントオフィス檜の吉野です。秋田市を拠点に小規模事業者・中小企業向けの経営コンサルティングを行っています。このブログは今まで起業支援を行っていく中で得られた知識と経験に基づき書いています。
さて、前回の記事と関連した内容を書いていきます。前回の記事を読んでいなくても大丈夫ですが、読んでおくとさらによいかもしれませんのでリンク入れておきます。
【5分で読める起業準備】幸せな起業への第一歩!顧客視点で考える自分資産の棚卸し術~|マネジメントオフィスひのき~
【5分で読める起業準備】第2回数値と感性で紐解く!あなたの宝物の見つけかたはコレだ!スキル棚卸しガイド|マネジメントオフィスひのき~
好きなことを見つけて、その好きなことで起業したい!という思いをもった人が次に考えると”よいこと”はなんでしょう?
十分なスキルを持っていたり、輝かしい実績を持って行ったり、とてつもない熱量を持っていたり、世にそういう人は一定数存在します(日本や世界で著名な起業家さんのようなレベル感 like スティーブ・ジョブズなど)
この記事でアドバイスしたいのはそういった人たちではなく、私を含む一般人のみなさんです。これは私の経験から言えるのですが、大多数の人は「えいやっ!」で起業するのには向いていません。そうした人たちにに必要なのは、株式を上場して大金を得る!や世界を変えるプロダクトを作るぞという意気込みではなく、もっと現実的な戦略が鍵なのです。
結論からお伝えします。現実的な戦略とは、”誰に対して、自分の好きなことや自分の好きなサービスを、いくらで、どう提供し、年間いくらぐらいの売上と手取りを確保するか?”その目安をつけていくことです。
ポイントを解説していきましょう。あくまで1stステップで必要なのは”目安”なのです。金融機関に融資を申し込み際に提出するレベルの細かい事業計画を作成する必要性は最初の時点ではないと私は思っています。まずは長い道のりを歩いてくために目安をつけるのです。ざっくりした道のりで構いません。
例えるならば、旅行の計画をざっくり立てるイメージです。秋田から東京に行こう、予算は8万円かな?みたいな感じです。この時点ではポイントポイントにピンを打つだけで十分です。東京のどこでご飯を食べようか?宿泊先はどこにしようか?飛行機のチケットはどこで買うか?などなど細かい部分を最初から詰めすぎると進みません(笑) 世に溢れている起業計画や事業計画は最初から一定以上の精度を求めることが多いです。やり方はそれぞれですが正解はないのですが最初はGoogle Mapにピンを打つイメージのざっくりしたものでOKだと私は思います。
【好きなこと】
【想定しているお客様は誰?】
【そのお客様に対して提供する具体的なサービスまたは製品内容】
【その事業はどれくらいの売上を目指すか?】
【自分はどれくらいの手取りが必要か?月間&年間】
こうした感じでざっくりとピンを打ちましょう。形式はなんでも構いません。そして可能であればこれは手書きで書いてください。経験上、デジタルよりもアナログの方がこうしたワークは向いています。
普通の人が起業で失敗せずに、ちゃんと生きていくことができるためには戦略がポイント。最初の一歩として上述した項目についてきちんと考えるのがオススメです。
まずはこのワークから始めて一緒に令和の時代を生き抜いていきましょう!あなたの成功を心よりお祈りしております。
マネジメントオフィス檜
吉野智人